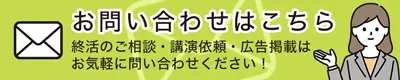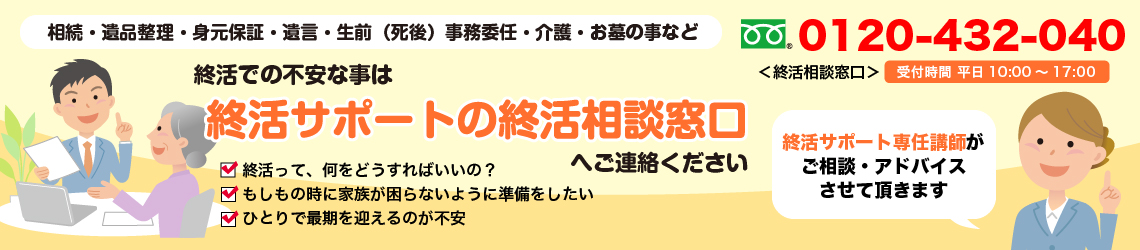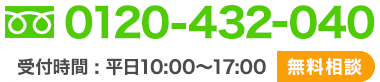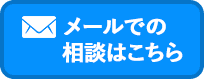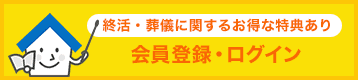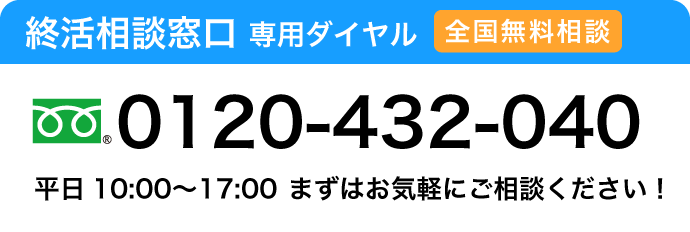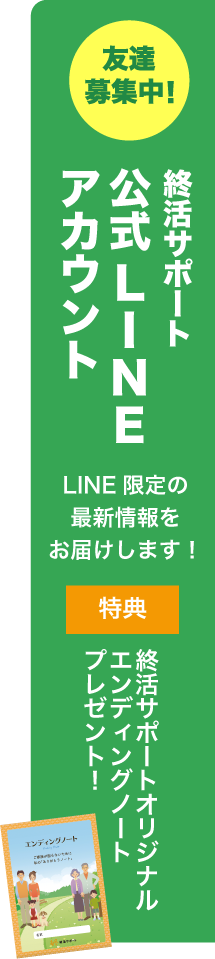家じまいは、理想の老後生活を送るうえで欠かせない大切な活動です。自分たちのためになるだけでなく、家族の負担も軽減できることから、終活の一環として取り組む人が増えています。家じまいをする方法はたくさんあり、選択肢によってかかる費用は大きく変動します。
売却するのが一般的ですが、古い家で売るのが難しそうな場合は、空き家対策で解体したり、リノベーションして賃付したりするのも、手段の一つです。今回は、家じまいをする方法3つとかかる費用を徹底解説します。家じまいをするデメリットや注意点も解説するため、迷ったり悩んだりしている方は、ご参考にしてみてください。
家じまいをする方法3つとかかる費用を徹底解説!デメリットや注意点も紹介
家じまいとは現在の住まいの将来を考えて実行すること

家じまいとは、現在の住まいを老後に備えてどうするべきか考えて、実行することです。自分の死後のことまで考えて、家族のためにする方も増えています。家じまいは住まいを手放すことから、マイナスなイメージを持たれている方も少なくありません。
慣れ親しんだ家を手放すのは名残惜しく、費用も発生するため、なかなか実行できていないという方も多いのではないでしょうか。しかし、家じまいをしないことによって起こりうる問題は、以下のように意外とたくさんあります。
- 将来誰も住まずに空き家になってしまう
- 家が古くなって管理や暮らしが大変になる
- 家の資産価値が下がって希望する金額で売却できない
家じまいは、自分たちの暮らしをより豊かにして、安定した老後生活を送るための前向きな活動です。家じまいをすることで、将来の家族の負担も軽減できます。
家じまいをする方法3つ
家じまいをする方法として一般的なのは、解体・売却・活用のどれかです。方法で悩んだときは、専門家に相談して判断することもできます。家じまいをする方法3つを紹介します。
家を解体して土地売却や活用する
家が古い場合や空き家になっている(なりそうな)場合は、思い切って解体する方法があります。土地は借りているなら返却、保有しているなら貸付か売却するのが一般的です。
家を解体するメリットには以下のようなものがあります。
- 固定資産税を節税できる
- 老朽化による倒壊リスクを減らせる
- 家を管理する手間や時間が必要無くなる
- 土地を保有している場合は売却しやすくなる
- 家の建て替え工事ができる
 家は誰も住んでいない空き家であっても、建っていれば固定資産税が発生します。持ち家を解体して賃貸住宅に住み替えれば、固定資産税を支払う負担がなくなるのは大きなメリットです。
家は誰も住んでいない空き家であっても、建っていれば固定資産税が発生します。持ち家を解体して賃貸住宅に住み替えれば、固定資産税を支払う負担がなくなるのは大きなメリットです。
老朽化による倒壊リスクを減らせたり、家を管理する手間や時間が必要無くなったりと、他にもメリットはたくさんあります。
家が古い場合は、解体して土地だけ売却したり貸付したりする方が、売れやすいのもメリットです。資金に余裕があるのであれば、家の建て替え工事をして自分たちが住む、家族に将来相続してもらうなどの手段もあります。
反対に、家を解体するデメリットには、以下のようなものがあります。
- 解体工事の費用がかかる
- 引越し先を探さなくてはいけない
- 売却や家族に相続はできなくなる
家を解体する場合は、50〜200万円ほどの工事費用が発生します。自治体によっては補助金を受けられることもありますが、上限があるため全額は賄えません。事前に住み替えの引越し先を探して、契約を済ませておく必要もあります。
家を解体してしまうと、当然売却や家族への相続はできなくなります。家の解体は売却ができない場合や、家族が相続を望んでいない場合の選択肢としておすすめです。
不動産会社に家を買い取ってもらう
家じまいで自宅を売却したいときは、不動産会社に買い取ってもらう方法もあります。不動産会社に家を売却する主なメリットには、以下のようなものがあります。
- 自分で売却先を探す手間がかからない
- まとまった資金をすぐに調達できる
- 仲介手数料を支払い続ける必要がない
 不動産会社との契約が成立すれば、家の売却は完了になります。自分で売却先を探す手間がかからず、まとまった資金をすぐに調達できるのは、大きなメリットです。仲介とは違って売却であるため、仲介手数料を支払い続ける必要もありません。不動産会社に家を売却するデメリットは、売却金額が低くなりがちなことです。
不動産会社との契約が成立すれば、家の売却は完了になります。自分で売却先を探す手間がかからず、まとまった資金をすぐに調達できるのは、大きなメリットです。仲介とは違って売却であるため、仲介手数料を支払い続ける必要もありません。不動産会社に家を売却するデメリットは、売却金額が低くなりがちなことです。
まとまった資金は手に入りますが、仲介貸付のように、定期的な家賃収入を得ることもできません。不動産会社の買い取り条件は厳しく、そもそも売却対象にならないこともあります。
売却先を探す手間や時間、不動産の資産価値などを考慮しながら、自分に合った方法で売却できるようにしましょう。
不動産会社に仲介とサポートを依頼して判断する
 家じまいで解体、売却、貸付、どうすればいいか悩んだときは、不動産会社に仲介とサポートを依頼して判断するのがおすすめです。不動産会社にまずは家の資産価値を査定してもらい、どの選択肢が理想的であるかを、一緒に考えてもらいましょう。
家じまいで解体、売却、貸付、どうすればいいか悩んだときは、不動産会社に仲介とサポートを依頼して判断するのがおすすめです。不動産会社にまずは家の資産価値を査定してもらい、どの選択肢が理想的であるかを、一緒に考えてもらいましょう。
不動産会社に相談するメリットは、専門家に判断してもらえることと、売却や貸付をする場合はそのまま契約を依頼できることです。私たち「終活サポート」では、終活不動産と業務提携をし終活に特化した不動産サービスを提供しています。
家じまいをしたい方の状況や希望をお伺いし、理想の住まいの終活ができるよう、徹底サポートさせていただきます。終活の一環としてご自分の老後のために、家族のために、家じまいをご検討している方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
- 関連記事
- ご提案事例のご紹介とお客様の声
- ご相談はこちら
家じまいにかかる費用は不動産の手放し方で決まる
家じまいにかかる費用の相場は、50万円〜数百万円以上までと幅広くなっています。家じまいにかかる一般的な費用相場を、項目ごとにまとめてみました。
| 30坪戸建てで家を解体する場合 | |
| 項目 | 費用 |
| 荷物整理を不用品回収業者に依頼 | 10〜30万円 |
| 住み替えの転居初期費用 | 30〜50万円 |
| 引越し作業を業者に依頼 | 5〜10万円 |
| 解体工事 | 50〜200万円 |
| 不動産の仲介手数料 | 売却価格の5%以内 |
| 測量 | 10〜50万円 |
| 印紙税 | 5,000〜1万円 |
| 譲渡所得税 |
(保有期間5年以下のとき)税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%) (保有期間5年超えのとき)税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%) |
選択する方法によっても、発生する費用は大きく変わってきます。 こちらの表の項目は代表的なものの一部であるため、実際にはその他諸経費も発生します。 家じまいの費用をなるべく安く済ませるためには、不動産会社など専門家に相談するのがおすすめです。
利用料金の安い提携業者を紹介してもらえたり、的確なアドバイスを受けられたりします。 必要のない作業や手続きを省くこともでき、無駄なコストを削減できる可能性が高くなります。 手間と時間はかかりますが、なるべく業者に依頼せず自分たちで作業や手続きを進めることでも、費用は削減できます。
家じまいをするデメリットと注意点は家族で揉める可能性があること
 家じまいをする大きなデメリットは、家族で揉める可能性があることです。家や土地などの不動産は、相続の対象となります。自分たちにとっては手放したい古い家であっても、家族にとっては大切な実家で、将来住みたいと考えている可能性もあります。
家じまいをする大きなデメリットは、家族で揉める可能性があることです。家や土地などの不動産は、相続の対象となります。自分たちにとっては手放したい古い家であっても、家族にとっては大切な実家で、将来住みたいと考えている可能性もあります。
家は大切な資産であるため、手放すときは事前に被相続者となる家族と話し合いを行い、必ず了承を得るようにしましょう。相続問題含む家族間トラブルを防ぐためにも、独断で判断をしないことが大切です。
また、家じまいには費用と手間が発生する、新たな住環境に慣れないといけない、などの懸念点もあります。家じまいの方法にもよりますが、完了するまでに長い時間を要することもあります。
しかし、家じまいには住まいに関する不安を解消できて、将来の空き家対策や相続トラブル防止ができるなどの、大きなメリットもたくさんあります。家族で話し合いお互いに納得できるのであれば、家の資産価値が下がる前に、なるべく早く取り組み始めるのがおすすめです。
家じまいは老後の不安や負担を解消できる大切な活動(まとめ)
家じまいという言葉に、ネガティブな印象を持っている方は少なくありません。思い出のある住まいを手放すには勇気が必要、実家が無くなるのは悲しいなどの理由から、判断に悩む方も多いと思います。ただ、適切なタイミングで家じまいを行わないと、将来に自分たちや家族が苦労をする可能性があります。
誰も住まずに空き家になったり、資産価値が下がって低い金額でしか売却できなかったり、起こりうる問題がたくさんあるのが現実です。家じまいは、現実的に住まいという不動産資産に向き合い、理想の老後生活計画を立てるために必要な、前向きな活動です。
家じまいのことで悩んだり迷ったりしたときは、「終活サポート」にお気軽にご相談ください。
今日のポイント
- 家じまいとは現在の住まいを老後に備えてどうするべきか考えて実行すること
- 家じまいをする方法3つは「家を解体して土地売却や活用する」「不動産会社に家を買い取ってもらう」「不動産会社に仲介とサポートを依頼して判断する」
- 家じまいにかかる費用の相場は50万円〜数百万円以上までと幅広い
- 家じまいをするデメリットは費用と手間が発生する、新たな住環境に慣れないといけない、家族で揉める可能性があることなど
- 家じまいをすると老後の不安を解消できて日々の暮らしがより豊かになる
【監修】末藤 康宏(終活専門不動産 ディレクター)

これまでの略歴
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士/AFP/管理業務主任者/
福祉住環境コーディネーター/承継寄付診断士
介護職員初任者研修課程 修了

これまでの略歴
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士/AFP/管理業務主任者/
福祉住環境コーディネーター/承継寄付診断士
介護職員初任者研修課程 修了
終活に関連する記事

終活の本当の意味を知ろう!その理由と効果
[作成日]2024/12/02
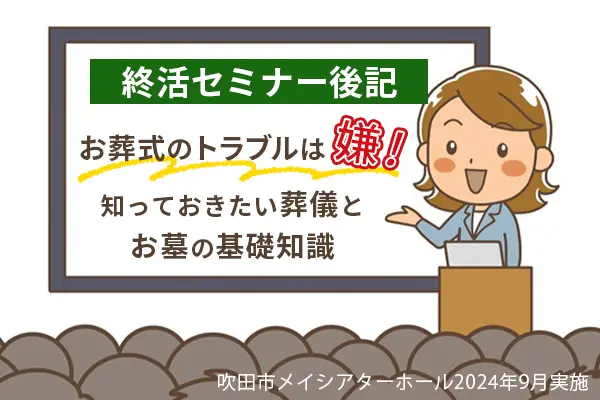
【終活セミナー後記】お葬式のトラブルは嫌!知っておきたい葬儀とお墓の基礎知識
[作成日]2024/10/30

終活の具体例|実際の体験談から見る成功例と失敗例
[作成日]2024/10/24
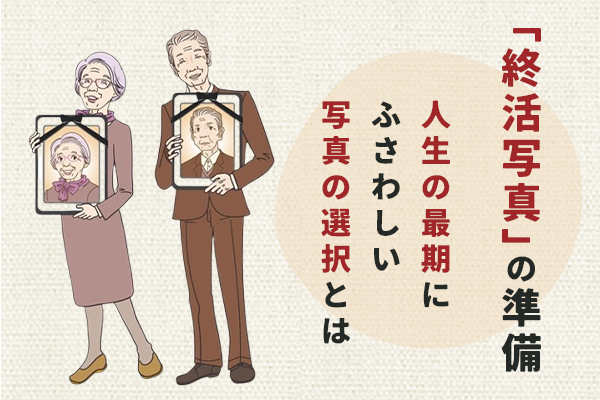
「終活写真」の準備|人生の最期にふさわしい写真の選択とは
[作成日]2024/10/17
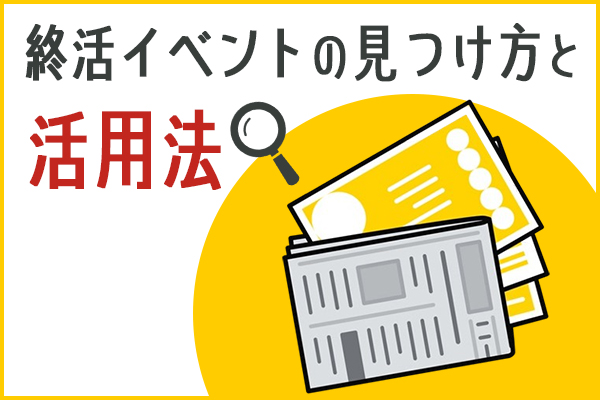
終活イベントの見つけ方と活用法
[作成日]2024/10/17
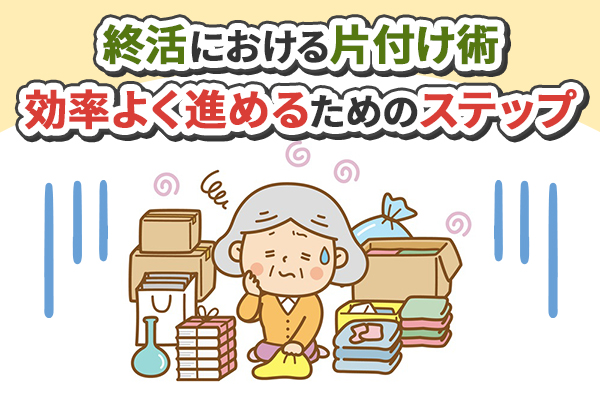
終活における片付け術|効率よく進めるためのステップとアドバイス
[作成日]2024/10/15
 終活サポート
終活サポート