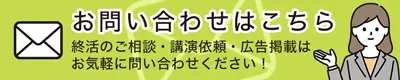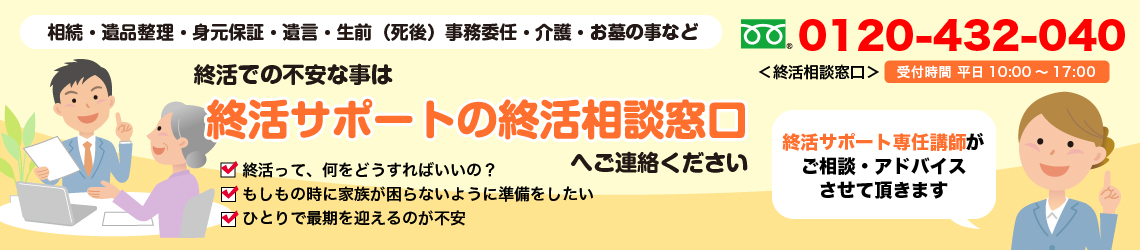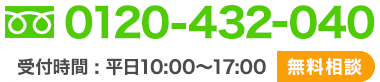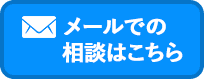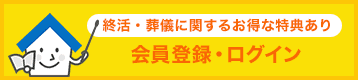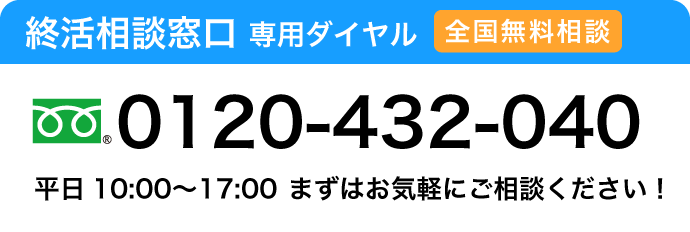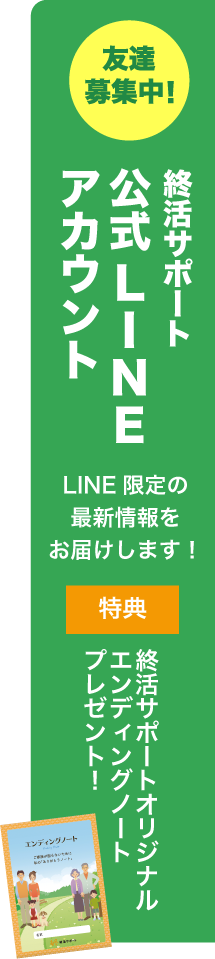葬儀の打ち合わせをする前に、1番最初に決めておく必要があるのが喪主となる人物です。そもそも喪主はどのように決めていったらよいのでしょうか?
葬儀の喪主は誰でもいいの?喪主の役割を細かく解説!
喪主は故人との関係によって決まる

通常喪主となるのは、遺族を代表する人になります。そして、それは故人との関係によって決まってくることがほとんどです。
仮に旦那さんが亡くなったとすると、その配偶者である奥さんが喪主を務めます。奥さんが既に他界されているようであれば、長男、もしくは長女にあたる関係の方が喪主になることが多いでしょう。
ですが、この場合において、奥さんがまだ存命であっても必ず喪主を務めないといけないというわけではありません。例えば奥さんの気持ちの負担が大きく、体調を崩してしまっているなどの事情が考えられる際には、その子供達の誰かが喪主の役割を果たすこともあります。
また、故人が未婚のまま亡くなって、後を継ぐ家族がいないというケースも存在します。その場合には、故人の兄弟や甥・姪などの親戚が喪主を務めることになります。その親戚すらいない場合には、友人が喪主になることもあるので、喪主は必ずしも親族でなければならないという決まりはありません。
このように、基本的には血縁関係の近い順番で、遺族の中から喪主にふさわしいとされる方が決まりますが、想定される状況によって変わってきます。とはいえ、喪主はお葬式において重要な役割があるため、それを担う方はしっかりと相談をした上で決めていく必要があります。
お葬式における喪主の役割
喪主を務める方が、お葬式の中でどういった役割を担っているのかを具体的に見ていきましょう。
葬儀社との相談
準備の段階から、実際にお葬式のプランを決めたり、各方面への連絡をしたりする。式場においても供花の順番や席順などを葬儀社のスタッフと相談をしながら決定をしていく。
寺院の窓口
菩提寺がある場合には、逝去の際の連絡やお葬式の日程決めの相談などをおこなう必要がある。また、戒名やお布施についても都度、お坊さんと話し合い、お葬式当日も食事の席に一緒につくこともある。
参列者への挨拶
式の前後の時間では、親戚や生前お世話になった方など、式に参列してくれた方との顔合わせや挨拶をする。通夜振舞いの食事や返礼品などを用意して、積極的におもてなしをする。
通夜時に故人への付き添い
最近では減ってきているものの、本来は通夜の晩から翌日の告別式まで故人の側に付き添って、お線香をあげ続けるために夜伽をするという役割がある。
この他にも、お葬式が終わった後には、お墓への納骨の段取りをつけたり、一周忌や三回忌などの法要に関する手配などについても喪主がおこないます。
葬儀場での喪主の立ち振る舞い
喪主は参列者や寺院の対応、供花の順番決めなどをおこなうため、開式時間の1時間〜1時間半前には葬儀場へ到着していることが望ましいです。葬儀場に着いた際は、周りから一目で見て喪主と分かるように、腰元のあたりに黒色の喪主リボンを着用します。
受付の説明や寺院への挨拶のタイミング等は、基本的に葬儀社のスタッフが声をかけてくれるでしょう。ですが、親戚関係の顔ぶれなどは葬儀社だけでなく、家族も把握しきれていない場合もあるため、控室の案内や席順の指定などは積極的に喪主のほうから声がけする場面も出てきます。
また、参列者に対しては、お礼の挨拶だけでなく故人との対面を案内したり、通夜振舞いの会食の席へと誘ったりするなどの対応が必要になることもあるでしょう。
このように、喪主は葬儀場で常に動き回って、各方面に気を遣う必要があるため、大変な負担がかかるものだと思われる方も多いでしょう。
お葬式の規模が大きくなっていけば、喪主の負担というのもさらに増えていくことになります。特に通夜の晩には、参列者や親戚が帰った後でやっと一息つけるといった状況にもなり得ます。だからこそ喪主を務める方は、事前に親族間でしっかりと相談した上で決定をする必要があるのです。
さて、無事に葬儀を終えた後に、通常の流れとしては葬儀費用の支払いをする必要があります。そうした際に、もしくは最初の見積もりの段階で、「喪主」ではなく「施主」という用語を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。それぞれの用語が意味するところは、大きく異なりますので、合わせて解説をしていきます。
葬儀費用を支払う人を「施主」として区別する
施主とは、言葉通り「(主に)施しをする人」と見て取れる通り、葬儀費用を支払う人のことをさします。
ですが喪主と施主は、ほとんどの場合同じ人物が務めています。そのため、あまり意識するポイントではないですが、なかには喪主と施主がイコールにならないようなケースも存在します。
たとえば、社葬や合同葬などで家族以外の方が葬儀費用の負担をするようなケースです。
この場合、遺族の中に喪主がいてお葬式が執り行われますが、最終的な葬儀費用の支払いの関係で会社が施主となります。
他にも家族間での取り決めで、故人の長男が喪主を務め、実質的な費用負担に関しては故人の妻(喪主の母)がする場合などは、喪主と施主が別の人物になります。このような際には、お葬式の最終的な領収書に記載される名前が施主のほうになるため、注意が必要になることもあります。
なぜなら、お葬式の後にしなくてはならない法律上の手続きや申請などは、多くの場合、代理でおこなうことができないため、そのための時間と手間がかかってしまう可能性があるからです。
もしも喪主と施主が別になるケースに該当する場合には、あらかじめこれらの点にも気をつけましょう。
喪主としてのマナー

豆知識①
- 服装
参列者の方を迎えるにあたって、喪主は特に服装を整えることがマナーとなっています。そのため、モーニングやシルクのワンピースなどの「正式礼装」や、ブラックスーツなどの「準礼服」を着用する必要があります。
また、華美なアクセサリー類は避けて、衣服にもシワがない状態にしておくことが望ましいです。急なことで喪服の準備が間に合わない方は、衣装店でのレンタルも可能なので、困った際は葬儀社のスタッフにも相談をしてみましょう。 - お焼香・献花
通夜・告別式・火葬に至るまで、仏式の場合にはお焼香、キリスト教や無宗教の場合には献花でお参りをします。
その際には、必ず喪主を務める方が1番最初におこないます。そのため、それぞれのお参りの流れや手順に関しては、事前に確認をしておき、間違えることがないようにしておくことが望ましいです。 - 挨拶
喪主は参列者に対しての個別の挨拶だけでなく、出棺前や会食の始めに、全員に対しての挨拶をする場面があります。普段使い慣れない言葉や言い回しがあるため、こういった挨拶の文言に関しても事前に準備をしておくことが必要です。
苦手な方に関しては、作った原稿を手元に用意しておいて、それを読み上げるといったやり方でも全く失礼にはあたりませんので、実際に以下の例文などを参考にして作成をしておくことをおすすめします。
- 関連記事
- 葬儀における喪主挨拶の文例
参列者への挨拶例文
豆知識②
喪主がする主な役割である、出棺時の挨拶と会食前の挨拶について、それぞれ簡単な例文を記載しますので、ぜひ参考にしてみてください。
● 出棺時の挨拶
遺族を代表いたしまして、ひと言ご挨拶を申し上げます。
私は、故人○○の長男○○でございます。
本日はお忙しい中、ご参列をいただき、また大変ご鄭重なるご厚志まで頂戴いただきまして誠にありがとうございます。
(故人の人柄・逝去までの過程)
このように大勢の方々にお見送りをいただき、故人もさぞかし喜んでいることと存じます。生前、故人に寄せられた皆さまのご厚情に対し、心より御礼を申し上げます。
未熟ではありますが、残された家族一同、皆さま方には、今後とも故人の生前同様のお付き合いをいただき、ご指導・ご鞭撻いただきますようお願いを申し上げます。
本日はありがとうございました。
● 会食前の挨拶
本日は、亡き○○のためにお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。
おかげさまで、滞りなく葬儀・告別式を済ませることができました。
ささやかではございますが、精進落としの席をご用意いたしました。生前の思い出話などを交えながら、お時間の許す限り、どうぞゆっくりとおくつろぎください。 本日は、誠にありがとうございました。
お葬式後に用意すること

豆知識③
お葬式が終わった後でも、喪主としてやらなくてはならないことが、いくつか出てきます。直近の数週間から数ヶ月以内のものだけを以下の3点にまとめました。
- 49日法要に向けた準備(仏式)
仏式では亡くなった日にちから49日を迎えるまでの間に、再度親族で集まって、49日法要を執り行います。
その際には、仏壇や戒名を記した本位牌を事前に用意しておき、寺院との日程調整をおこなう必要があります。 - 納骨先の選定・墓石屋の手配
菩提寺がない場合は、霊園や納骨堂へ納骨することが一般的です。まだ墓地を所有していない方は、納骨先を探さなくてはなりません。
また霊園墓地に関しては、墓石に名前を彫ったり、収骨場所を開けてもらうために、墓石屋を事前に手配しておく必要があります。 - 役所の手続き
お葬式が終わった後で、通常は領収書が発行されます。それを持って住んでいる地域の自治体を訪れれば、所定の手続きによって、5万〜7万円程度の葬祭費の支給を受け取ることが可能です。
他にも、年金受給の停止や名義変更などの細かい手続きがあるため、葬儀社や専門家に事前に聞いておくことをおすすめします。
【葬儀の喪主は誰でもいいの?喪主の役割を細かく解説のまとめ】
喪主は遺族の代表であり、お葬式の間はもちろんのこと、その後においても様々な役割を担う必要があります。とはいえ大切な人を亡くされた状況で、1人で全てをやろうとすると、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかってしまいます。
可能な限り周囲のサポートに頼るなどして、故人とのお別れの時間もしっかりと取れるようにすることが理想的です。
【監修】池原充子(終活専門相談員)

これまでの略歴
身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了
兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒

これまでの略歴
身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了
兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒
葬儀に関連する記事
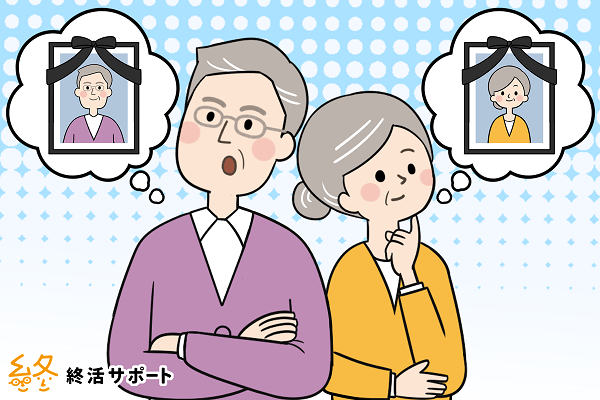
遺影写真はアプリの加工をしてもいい?作成のポイント7つを解説!
[作成日]2022/09/01
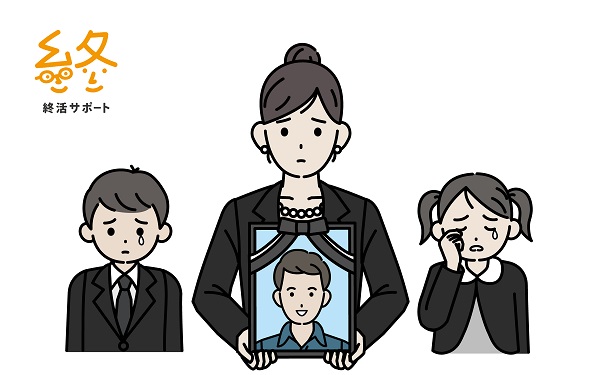
遺影とは?基本を5つの項目で徹底解説【飾る場所・処分方法・タブー】
[作成日]2022/08/08
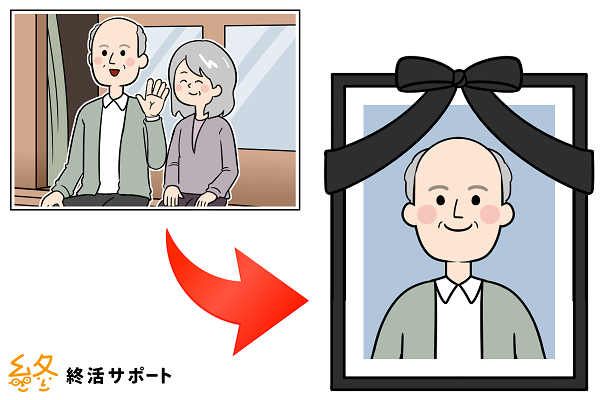
生前に遺影を用意するメリット3つ【料金・メイク・撮影の流れ】
[作成日]2022/08/08
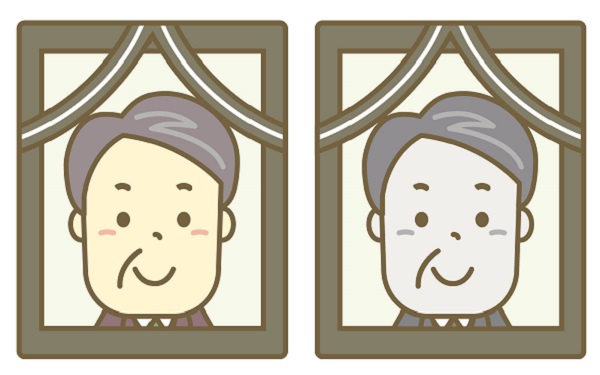
祖父が亡くなった際に必要な手続きや忌引き休暇申請についてご紹介
[作成日]2022/07/19
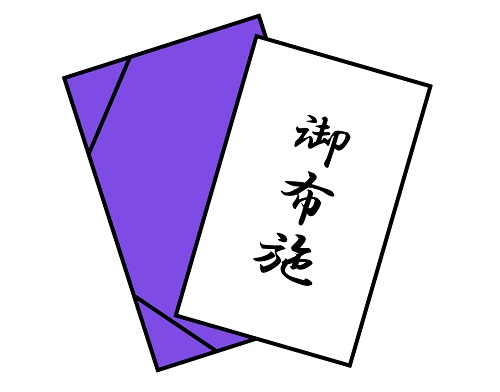
お布施を入れる封筒とは?入れ方から渡し方のマナー3選
[作成日]2022/06/01

命日にすることとは?祥月命日と月命日の違いやそれぞれの過ごし方について
[作成日]2022/05/09
 終活サポート
終活サポート