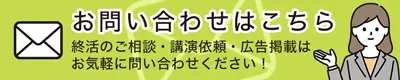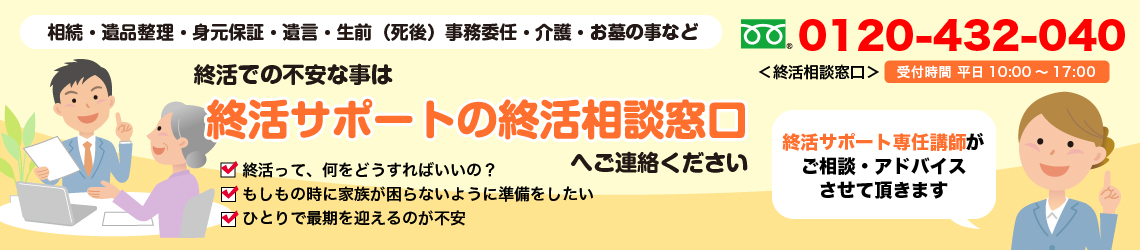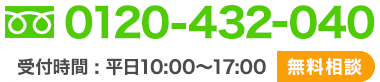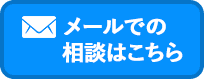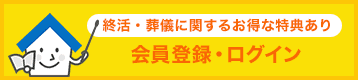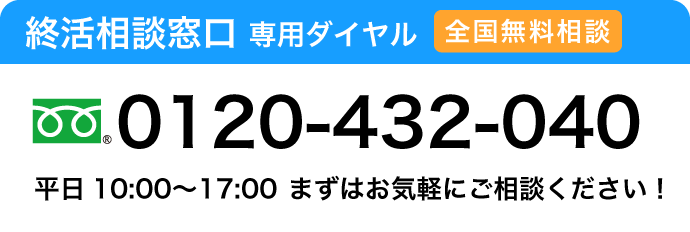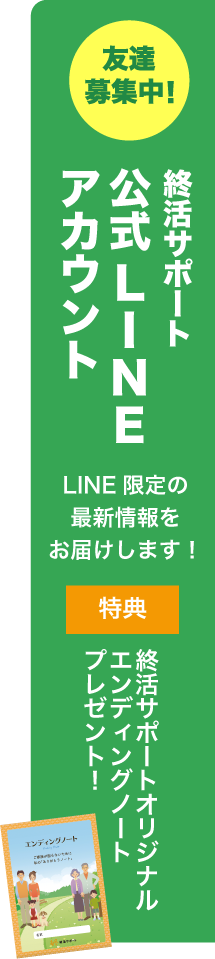供花というと参列者から出していただくもので、喪主にはあまり関係ないものと思われる方も多くいらっしゃいます。もちろん地域によっては慣習としてそのようになっている所もありますが、ほとんどの場合において喪主が供花を出すことは問題ないとされています。ただし、供花に関しては出す際の決まり事や、気をつけるべきマナーがあり、喪主の立場としては事前にしっかりと把握しておきたいものです。
今回はそれらと合わせて、供花に立てる札の名義に関する並び順や、供花を頂いた方へのお返しが必要かどうかという点に至るまで、それぞれ詳しくご紹介させて頂きます。供花は祭壇脇に飾られるため、参列者の目にも留まりやすい部分です。大事な場面で失敗をしないためにも、あらかじめ内容をしっかりと把握しておきましょう。
喪主は供花を出す?供花を出す際の注意点について
祭壇の両脇に飾られる供花とは
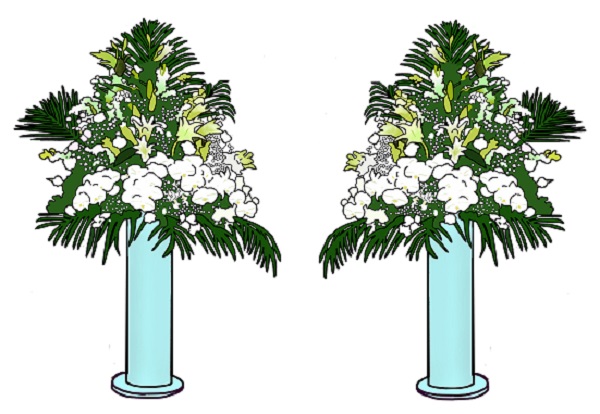
供花というのは故人に対して、感謝の気持ちと弔いの気持ちを込めて送る生花です。結婚式ではお祝いの気持ちを込めてお花を用意しますが、お葬式や法事などの弔事において出される供花は、哀悼の気持ちを表すものとして非常に重要な役割を果たしています。
近年のお葬式において、供花は一般的に祭壇脇に飾る生花のことを指していますが、一昔前は大きな飾り物がついた「花輪」が葬儀場の外に出されることが多くありました。今でも地域によっては花輪が主流のところもあるようですが、都市圏を中心にほとんどの場所ではアレンジメントされた生花のことを供花としています。
祭壇脇に飾られる供花の費用としては、概ね10,000円〜20,000円のものが主流です。飾る際は高さをつけて遠目からでも目立つようにするための台が付けられています。供花の個数は、1基、2基、3基・・・と数えられ、1人が2基出す場合にはそれぞれ両脇に配置されるようになるため、1対と数えられるようになります。
また、亡くなって自宅安置されている時に、故人の枕元に供える生花として枕花というものもあります。枕花の場合、費用として3,000円〜10,000円のあまり大きくならない程度の供花を送ることが一般的です。
お葬式の形式によって花の種類が異なる
生花は様々な種類があり、またそれぞれの花の意味する特徴から、お葬式に使われる生花というのはある程度限られています。その中でも昔から多く使われてきたのは、菊・百合・胡蝶蘭などの生花です。
仏教式や神道式など、日本の宗教に基づくお葬式の場合、特にこれらの生花を中心にしたアレンジメントをよく目にすることでしょう。
一方でキリスト教のような、西洋式のお葬式の場合は、カーネーションやトルコキキョウ、バラなど多彩な種類の生花で構成されることが多いです。
ですが、時代の変化と共に白木祭壇ではなく花祭壇が主流になってきたため、仏教式や神道式のお葬式においても、使用される生花の種類が変わってきています。そのため、たとえ仏式の場合でも、菊ではなくカーネーションなどの洋花が多く使われていたり、菊が一切入っていないような供花が祭壇脇に並んでいることも増えてきました。
また、全体的な色合いについても、昔は白上がりのもので統一されていたものが、ピンク系やブルー系など、カラフルな仕上がりになっているものも見かけられるようになってきています。
葬儀の荘厳なイメージを持たれる方には驚かれることも多いですが、実際は様々な生花が飾られることで祭壇全体がパッと明るい印象になることを好ましく思う方が多いため、今後は洋花を中心とした供花が主流になってくるでしょう。
葬儀の供花は誰が出す?
基本的に供花は、故人との関係に限らずに誰でも出すことが可能です。そのため喪主や親族はもちろんのこと、友人や会社関係などの名義で出されることもあります。
ただし地域によっては、風習の違いにより喪主の名義の供花が必要とされないところもあります。また、喪主ではなく施主という名義で出す地域などもあるため、それぞれの風習に応じた出し方を事前に確認しておくようにしましょう。
供花を出したい場合には、葬儀社を通じて依頼することがほとんどです。逆に葬儀社以外のルートでお願いをする場合は、お断りをされてしまう場合もあります。これは祭壇や供花を並べた際に、1基だけ違う供花が入っていると、その供花だけ極端に目立ってしまうという理由があるからです。
注文をする際に気をつけなくてはならないのは、供花に立てる札に記載する名前と支払い方法についてです。名前に関して、FAXやメールなど書面で伝えられるものであればよいのですが、特に電話での注文をする際は気をつけなければなりません。
例えば、斎藤という苗字の方が供花を出す場合、「斎」の字は「斉」・「齋」などの複数の漢字の候補があります。他にも会社関係であれば、株式会社という表記が会社名の後にくるのか、前にくるのかといった点なども細かく指定をしておく必要があります。
供花の支払い方法については、銀行振り込み、もしくは斎場で葬儀社のスタッフへ直接現金で支払うか、いずれかの方法で対応しているところがほとんどです。現状はクレジットカードやキャッシュレスでの対応をしている葬儀社はまだまだ少ないため、普段現金を持ち歩かない方は注意しましょう。
供花を出す際のマナー

供花は斎場や祭壇に飾るための準備の兼ね合いもあるため、余裕をもって注文をしておく必要があります。そのため、なるべくなら通夜の前日まで、遅くとも当日の午前中には注文を済ませておくほうがよいでしょう。
その他に供花を出す際に気をつけておくべき点やマナーについてもまとめていますので、遺族、親戚、一般のそれぞれの状況に分けて見ていきましょう。
● 遺族
喪主としての供花は基本的には出されることが多いものの、地域によっても違うので確認が必要です。他、遺族でそれぞれ供花を出す場合、長男や長女など近い関係であれば個人名の表記にするのが一般的です。
ただし結婚している夫婦であれば、連名で出しても構いません。お孫さんなどが複数いて、3人以上の名前で共同して出す場合には、一同という表記にして「孫一同」といった表記にします。
● 親戚
それぞれの名前で出す方もいれば、故人の兄弟や甥・姪にあたる関係で一同の表記で出すこともあるでしょう。特に兄弟にあたる関係の場合、「兄弟」「兄妹」「姉妹」など、家族構成によって表記が変わってくることもあるため、注意が必要です。
● 一般
複数の友人などで1基の供花を出す場合には、連名での表記になります。その際の名義札の文字は、3名分までであればある程度の遠目からでも見えますが、4名以上となるとかなり小さくなってしまいます。
そのため、共同で出す場合の名義の表記については、人数に応じて一同の表記にするなどの対応が必要です。
故人との関係性で供花の並び順を整える
祭壇脇に供花を飾る際には、並び順を整える必要があります。こちらも地域によって違いがありますが、一般的には喪主が1番となり、それ以降に子供、孫、親戚(兄弟)、親戚(甥・姪)などと続いていきます。続いて友人関係や会社関係の供花が並ぶようになります。
会社関係に関しては、故人と関係の深いところから先に並べ、その後に取引先や子供の関係の会社の名義が連なっていくような順番です。
場所としては、祭壇を正面に見て、右側の祭壇に近い箇所が序列の高いところになります。その次は左側の祭壇に近い箇所です。これを交互に繰り返していき、2段目、3段目と場所が決まっていきます。こうした順番に関しては、開式前に喪主が関係性やバランスを葬儀社のスタッフと相談をしながら決めていきます。
ただし、供花の本数が多い場合は、名義の札を立てるのではなく、芳名版を利用して並べることもあります。その際は、明確に順番をつけずに、あいうえお順で並べられることが多いです。
人によっては供花の順番や序列を気にする方もいらっしゃいますので、詳しい決め方に関しては、家族やスタッフと慎重に相談をしながら進めていくようにしましょう。
家族葬における供花の出し方
近年では、広く一般的に訃報を知らせずに家族や親戚を中心とした家族葬が増えてきています。そうした家族葬では、喪主や故人の意向によって香典辞退としていたり、供花辞退としているような場合もあります。
家族葬の参列者の中には祭壇を目にした際にお花が少ないと感じてしまって、自分が供花を出してあげたいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、あくまで遺族側の意向でもあるため、無理に出してしまうことは、却って失礼にあたってしまいます。勝手な判断で供花を出すといったことは避けるようにしましょう。
また、勤めている会社によっては、弔事の際の決まり事として供花が出るようなところもありますが、こちらも事前にしっかりとお断りをしておく必要があります。
どうしても供花を出したいという場合には、必ず遺族側に相談をするようにしましょう。あるいは供花を出す以外の方法を取ることをおすすめします。例えば供物としてお菓子や果物を持参する、といった方法などが挙げられます。
家族葬では特に、参列者に対しての負担をかけたくないという意向がはっきりと表れることも多いため、決して自分本位な贈り方にならないように注意しましょう。
供花にお返しは必要?
供花に対してのお返しについては、考え方が分かれるところではありますが、香典とは違うため基本的には必要ありません。供花はあくまで故人に向けた気持ちとして頂くものなので、特に気を遣うことなくありがたく頂戴するようにしましょう。
それでもやはり何かお返しをされたいとなった際には、お葬式の後にお礼状を出して感謝の意を伝えることをおすすめいたします。あるいはお香典返しの品物と一緒に、何か別の品物を用意して渡されるのもよいでしょう。
ただしあまり高価な品物を渡してしまうと、却って相手も気を遣って恐縮してしまう状況にもなりかねないため、注意が必要です。供花のお返しのタイミングに関しては、葬儀後すぐに渡すのではなく49日のお返しと合わせて準備をすれば、手間を省くことができます。
会社関係などに関してのお返しは特に気にする必要はありませんが、所属している部署など、普段接することが多いところから頂いた場合に関しては、小分けにできるようなお菓子などを持参してお礼の挨拶を述べるなどの対応をされるとよいでしょう。
供花の本数が多い場合などは、出された方の名前を把握しきれないこともあります。そうした際には葬儀社へと相談をすれば、供花名義をリストにまとめたものをもらうことができますので、それをもとに必要な方へのお礼をするようにしましょう。
喪主は供花を出す?供花を出す際の注意点のまとめ
祭壇脇に飾られる供花について、一昔前は菊などの和花が主流でしたが、最近ではカーネーションのような洋花が用いられる機会が増えてきています。また、色合いに関しても白一色といった統一感を重視するのではなく、ピンクや赤色などの様々なアレンジメントがされるようにもなってきました。
供花は故人に対しての感謝と弔いの気持ちによって出されるものです。喪主としてはそうした想いをしっかりと受け止めて、供花を出していただいた際は、有り難く頂戴しましょう。
一方で、近年は家族葬が増えており、供花辞退ということも珍しくない時代となってきました。参列者の立場としては、そうした決め事についてあまり理解せずに、勝手な判断や自分本意な気持ちだけで出してしまうと、かえって失礼にあたる場合があります。
そのため、ご供養の気持ちはしっかりと持ちつつも、遺族の意向も汲み取った上で適切に対応していくことが大切です。
【監修】池原充子(終活専門相談員)

これまでの略歴
身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了
兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒

これまでの略歴
身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了
兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒
葬儀に関連する記事
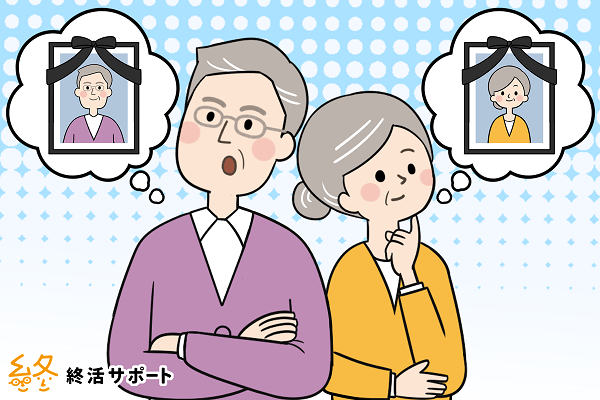
遺影写真はアプリの加工をしてもいい?作成のポイント7つを解説!
[作成日]2022/09/01
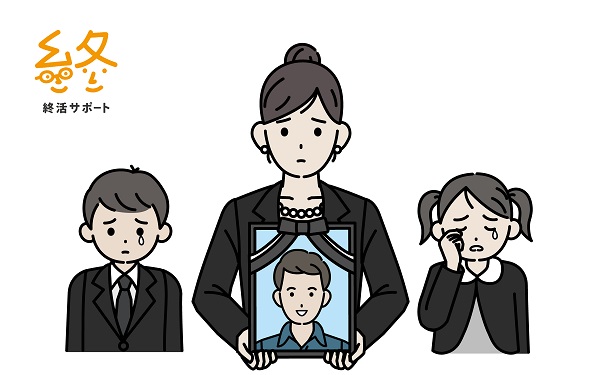
遺影とは?基本を5つの項目で徹底解説【飾る場所・処分方法・タブー】
[作成日]2022/08/08
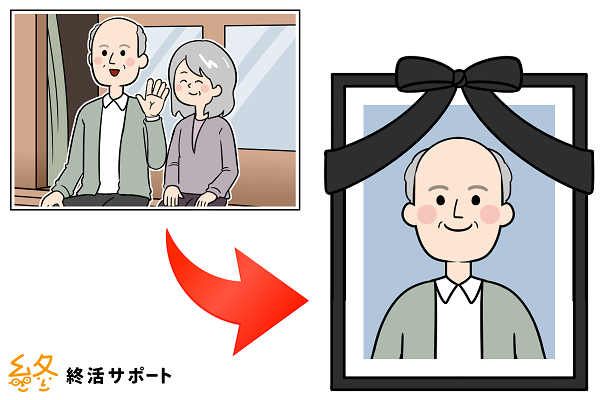
生前に遺影を用意するメリット3つ【料金・メイク・撮影の流れ】
[作成日]2022/08/08
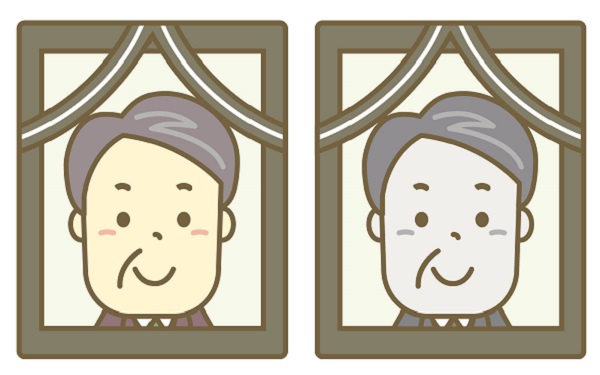
祖父が亡くなった際に必要な手続きや忌引き休暇申請についてご紹介
[作成日]2022/07/19
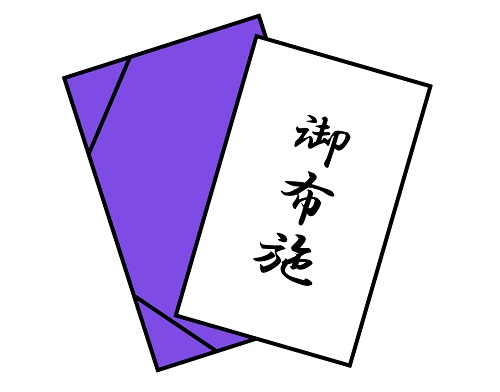
お布施を入れる封筒とは?入れ方から渡し方のマナー3選
[作成日]2022/06/01

命日にすることとは?祥月命日と月命日の違いやそれぞれの過ごし方について
[作成日]2022/05/09
 終活サポート
終活サポート